
|

|
| 函館市北洋資料館
函館と北洋との結びつきは江戸幕府が箱館に奉行を置き樺太沿岸の漁業を手がけたことに始まり、 昭和63年まで母船式サケ・マス漁業の基地としての役割を果たしてきました。 当館は、厳しい北洋の自然と戦いながら生きてきた先人たちの歩みについて学べる施設です。 |
↓
| 五稜郭公園
|

|

|
| 箱館奉行所 |

|
ホテル発→北方民族資料館→文学館→旧イギリス領事館→旧函館区公会堂→カトリック元町教会→地域興産センター→赤レンガ倉庫→ ホテル(泊)
| 函館駅前 |

|
| 3連泊した函館駅横のホテル。ラ・ジェント・ステイ函館駅前 |

|
| JR函館駅 |

|
| 駅前広場のあるモニュメント 親子のブリッジ |
| 函館市北方民族資料館
函館市北方民族資料館は、旧日本銀行函館支店(1926年築)を改装し、市立函館博物館所蔵民族資料および石川啄木関連資料を展示する「函館市北方民族・石川啄木資料館」として平成元(1989)年11月に開館しました。その後、旧第一銀行函館支店(1921年築)を改装した函館市文学館に石川啄木関連資料を移管して、平成5(1993)年4月に「函館市北方民族資料館」としてリニューアルオープンしたものです。 同館は、市立函館博物館が所蔵している、アイヌやウイルタなどをはじめとした貴重な民族資料を展示しています。 |
↓
| 函館市文学館
函館市文学館は,函館ゆかりの作家の業績と風土に根ざした土着の文学空間を視野に入れ,函館が育んだ多くの文学者と文学空間を永く後世に顕彰し,語り継いでいくことを目的に,平成5年に開館しました。 詩人・石川啄木,作家・亀井勝一郎や久生十蘭,佐藤泰志,彫刻家・挿絵画家の梁川剛一などの展示をご覧いただくことができます。 |
↓
| 旧イギリス領事館
函館市旧イギリス領事館は函館が国際貿易港として開港した1859年(安政6)年から75年間、ユニオンジャックをかかげ続け、異国情緒あふれる港町函館を彩ってきました。 数回の火災にあったのちこの場所に再建しましたが、再び火災により焼失し、現在の建物は1913(大正2)年、イギリス政府工務省上海工事局の設計によって竣工し、1934(昭和9)年に閉鎖されるまで領事館として使用されていました。 1979(昭和54)年に函館市の有形文化財に指定され、1992(平成4)年の市制施行70周年を記念して復元し、この年から開港記念館として一般公開をしてきました。 2009(平成21)年3月、開港150周年を機に展示内容を一新し、開港都市のシンボルとして新たな歩みを始めました。 |
↓
| 旧函館区公会堂 重要文化財 旧函館区公会堂は明治43年(1910)に建てられた、洋風建築の代表的建物です。 昭和49年(1974)に国の重要文化財に指定されました。 気品漂う内部には華やかな雰囲気の家具や調度品が展示されています。 |
↓
| カトリック元町教会
カトリック元町教会は、12世紀のゴシック建築様式を用いた、高くそびえるとがった屋根の大鐘楼が特徴です。徳川幕府が発布していたキリシタン禁教令が廃止されるのに先駆け、キリスト教宣教再開の象徴として、横浜と長崎に建立するカトリック教会と並び、国内では最も古い歴史を持ちます。 |
↓
| カール・レイモン歴史展示館
「カール・レイモン歴史展示館」では、波瀾万丈な人生を送った、カール・レイモンの人生を多数のパネルで紹介しております。また、展示品やカール・レイモン語録なども取り揃えており、カール・レイモンのルーツを知る事ができます。 なお、レイモンハウス元町店1階では各商品をご購入いただけるとともに、ここでしか味わえないファーストフードを取り扱っております。 |
↓
| 函館市地域興産センター
|
↓
| 金森赤レンガ倉庫 函館の西部地区にある金森赤レンガ倉庫は、長崎から函館に移り住み、輸入雑貨や船具などの販売を手掛けた初代渡邉熊四郎が1887(明治20)年に既存の建物を買い取り営業倉庫業に乗り出したのが始まりです。海運業の活況により、荷物の取扱量が年々増加したことで倉庫を増築し、営業規模を拡大していきました。 そんな最中、1907(明治40)年に発生した大火で倉庫6棟が焼失し、代わりとなる不燃質の倉庫として1909(明治42)年に建てられたのが現在の建物です。その後、流通の多様化や北洋漁業の衰退などに伴い1988(昭和63)年に飲食店や土産物店が入居する複合施設へと姿を変え、観光スポットとなりましたが、現在でも数棟が現役の営業倉庫として使用されています。 金森赤レンガ倉庫として営業する7棟の施設は、「函館ヒストリープラザ」「金森ホール」「金森洋物館」「BAYはこだて」に分かれていて、飲食店や土産物店などが軒を連ねています。また、冬には倉庫の目の前で、一大イベント「はこだてクリスマスファンタジー」が開催されます。 |
↓

|
2023/12/19 (火)
ホテル→湯浅神社→トラピスチヌ修道院→函館市熱帯植物園→函館山展望台→→ホテル(泊)
| 湯浅神社 松前藩主高広が幼少の折に重い病にかかり、母の夢のお告げによってこの地の温泉に入浴したところ快癒したという故事が伝わっており、湯倉神社にはこのお礼として奉納された鰐口(わにくち)が今も残っています。 |
 |
| 御本殿 神社の代表的な建築様式の一つ「流造」で建てられた現在の御本殿は、昭和16年に御造営された。華美な装飾はないが、先人から受け継がれてきた匠の技が注がれた荘厳な雰囲気の建造物である。 |

|
| 大鳥居 |
| トラピスチヌ修道院 |

|
| 正門 |

|
| 聖ミカエル |

|

|
| 慈しみの聖母像 |

|

|
| ルルドの聖母 |

|

|
| 雪で石段が滑る危険性があり、通行禁止。ロープで遮っていた。残念。 |

|
| 函館市熱帯植物園
|

|

|
| 函館市の熱帯植物園では毎年この時期に湯の川温泉から湯を引いていて、温度はサルが気持ちよく入ることができる41度に設定されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
| 函館山展望台 |

|

|

|

|

|
| 青函連絡船記念館 |

|
| 岸壁 |

|
| 摩周丸 |

|
| 摩周丸 |

|

|
| 大アンカーと主動輪 |
| 大通公園 |
| 北海道庁旧本庁舎 改修工事中 2025年にリニューアルオープンの予定 北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)は、重要文化財として国の指定を受けた、北海道を代表する歴史的建造物ですが、昭和43年の復原工事以来50年以上が経過し、各所に劣化が著しく進行しています。 2018年(平成30年)の北海道命名150周年を契機として、先人から受け継いだ貴重な財産である「赤れんが庁舎」の歴史的価値を保存し、次の世代へ引き継ぐため、大規模な改修を行うこととなりました。 この改修を機に、赤れんが庁舎を北海道観光の呼び水となるよう、国内外に向けた北海道の歴史文化・観光情報発信拠点として位置づけ、館内の展示や活用方法を全面的に見直し、施設の魅力向上を図ります。 |
| 北海道庁旧本庁舎 八角塔がこの建物の一つの特徴でこの塔にはお馴染みの★のマークが燦然と輝いています。[史跡 開拓使札幌本庁 本庁舎跡および旧北海道庁本庁舎]と記されています。その意味では道庁構内は歴史的にも大きな役割を果たした場所でもあります。 |
| 北海道庁旧本庁舎 |
| 紅葉( 黄色く )した銀杏の大木 |
| 北海道庁旧本庁舎 |
| 北海道庁旧本庁舎 説明板 |
| ホーレス・ケプロンの像 開拓使が招聘した外国の指導者の中で最初に来日したのが[ホーレス・ケプロン]でした。ホーレス・ケプロンは、アメリカ合衆国政府農務長官時代の1871年(明治4年)渡米していた黒田清隆の懇願を受け入れ、現職を辞して招聘を受け入れ同年訪日し1875年(明治8年)5月帰国するまで、開拓使御雇教師頭取兼開拓顧問として北海道の開発に大きな貢献を果たされました。ケプロンは、道路建設、工業、農業など各分野で建設的な提言を行いこれらの施策が今日の札幌はもとより北海道の開発の基盤造りの原点となつています。(北大付属図書館 ) ケプロンは、日本に滞在中多くの事業を提案しましたが、中でも札幌農学校、開拓使麦酒醸造所などは本府札幌にとっても大きな事業の一つであり、今日の札幌の発展に多くの足跡を遺しました。大通公園10丁目には、ホーレス・ケプロンと黒田清隆の像が並立して建立され東に向かって発展を続ける道都札幌の未来を見つめ続けています。ケプロンは、札幌の歴史を築いた先人の一人として高く評価されています。 (像の説明版から) |
| 黒田清隆の像
1870(明治3)年、薩摩藩出身の黒田清隆(くろだきよたか)が開拓次官に任じられ、開拓使の実質的なトップになりました。黒田は開拓使十年計画を策定し、明治政府に北海道開拓の重要性を認めさせ、巨額の予算を引き出すことに成功したのです。 黒田は海外からさまざまな分野の外国人技術者を招聘(しょうへい)し、アメリカの開拓を手本として、鉄道や道路の敷設、炭鉱開発、ビールや砂糖の製造、洋式農業の導入、札幌農学校開校など、ありとあらゆる事業を同時に展開しました。そして、1874(明治7)年には北方警備、開拓を兼任させるために屯田(とんでん)兵制を開始。生活に困窮する士族を移民させ、北海道へと入植させていきました。 |
| 北海道神社 「北海道神宮」は1869年に創建さ、北海道の拡大発展の守護神です。火災で焼失した後に再建された、北海道を代表する神社として大変人気があります。参拝だけでなく、桜や梅の名所としても有名で、御朱印や御守りも人気です。 From NET |
| 北海道神社 大鳥居 |
| 北海道神社 手水舎 |
| 北海道神社 |
| 北海道神社 |
| 北海道神社 |
| 北海道神社 |
| 北海道神社 |

|
| 北海道神社 末社 開拓神社 |
| 北海道神社 末社 開拓神社 |
| 北海道神社 末社 鉱霊神社 北海道には良質の石炭や、金属の鉱脈が各地に存在していたため、最盛期には数多くの石炭鉱山と金属鉱山が稼働していた。夕張市や美唄市などは炭鉱によって発展していった町として有名。しかし、炭鉱により発展して行く一方で、度重なる鉱山事故により殉職してしまう者も多かった。その後、鉱山は国策の変更や鉱脈自体の枯渇などにより次々と閉山してしまう。 札幌鉱霊神社は、殉職者の御霊への感謝の気持ちとその功績を敬い祭祀を営むため、昭和18年(1943)に当時の札幌鉱山監督局長久保吉六氏の提唱により同局の前庭に鉱霊社として建設。建設日の6月25日には鎮座祭並びに第一回合祀祭が盛大に行われた。その後、昭和24年(1949)に北海道神宮の末社として、穂多木神社と開拓神社の間に遷座し、その時に札幌鉱霊神社と改められた。以来6月25日は例祭日と定められ祭祀を営むと共に、新たな殉職者も併せて祭り本道鉱業の安全と発展を祈願している。 |
| 北海道神社 末社 鉱霊神社 |
| 北海道神社 末社 穂多木神社 |
| 北海道神社 末社 穂多木神社 社の前にはブロンズ製の精悍な顔をした一対の狛犬が鎮座し、参拝者を出迎えてくれる。北海道拓殖銀行に永年勤務功労のあった物故役職員の御霊を祀るため昭和13年(1938)本店の屋上に建立された。 北海道拓殖銀行は平成9年(1997)に経営破綻し、平成11年(1999)に解散した。もともとは明治33年(1900)に始まった北海道の開拓事業(拓殖)を支援するため、資本を供給することが目的の特殊銀行として設立。その後北海道経済の発展にともない事業を拡大したが、終戦後はGHQにより業務停止を命じられた。昭和25年(1950)には拓銀法廃止により普通銀行へ転換し、同年、穂多木神社も札幌神社(現北海道神宮)境内に遷座され、現在に至る。 |
| JRタワー JRタワーは、札幌市中央区に所在する札幌駅の駅ビル型複合商業ビル。北海道で一番の高さを誇る超高層ビルである。 From WIKI |

|
| 38階 展望ロビーの男子トイレ |

|
| 展望ロビーからの夜景 |

|
| 展望ロビーからの夜景 |

|
| 展望ロビーからの夜景 |

|
| 中島公園 |

|

|

|
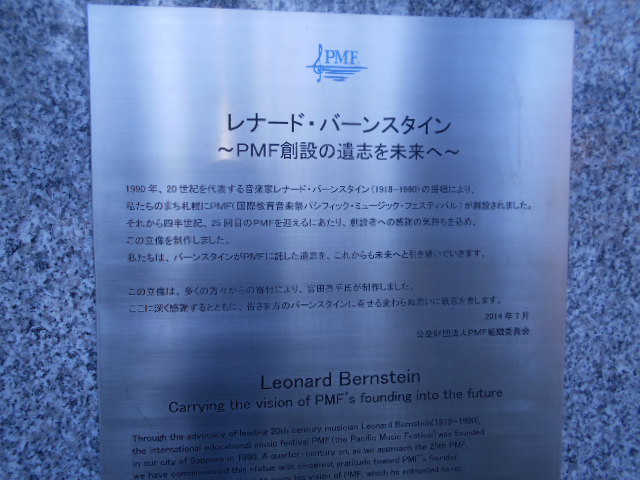
|

|

|

|

|

|
| 水族園 AOAO SAPPORO |

|